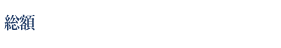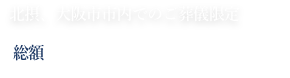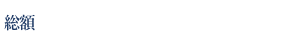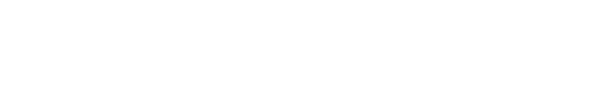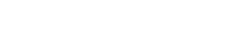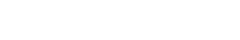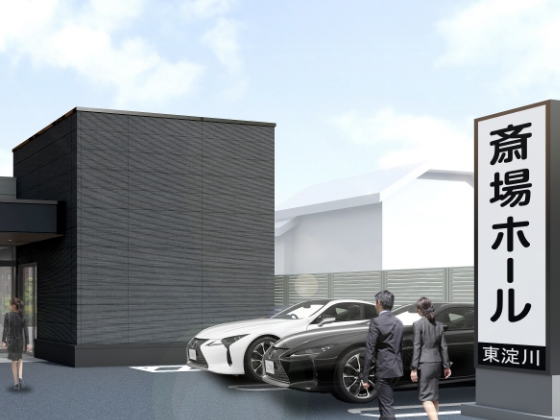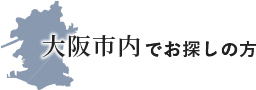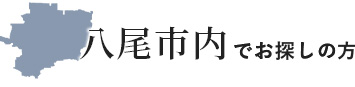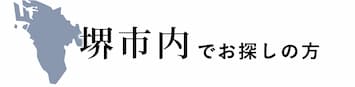大阪府茨木市は、北摂三島地域に位置する施行時特例市です。中枢中核都市にも選定されており、1970年に吹田市で開催された日本万国博覧会(大阪万博)により、急激に都市開発が進んだ自治体でもあります。隣接自治体として、吹田市、高槻市、箕面市、摂津市、豊能郡豊能町、そして京都府亀岡市の6つがあります。面積は76.49㎢、人口は2024年6月時点で286,038人です。男女比では、男性が137,718人、女性が148,320人となっており、世帯数は日本人のみで130,309世帯あります。
市内は南北で印象が大きく異なっています。北部は田んぼや山が広がる田園地帯となっている一方、南部は交通網が発達している関係で、住宅地やビルなどの建物が増加傾向にあります。主要な交通網としてはJR東海道線や阪急京都線、大阪モノレールなどの鉄道のほか、名神・新名神といった大きな高速道路も通っています。また、近畿自動車道や大阪中央環状線もあり、大阪市や神戸市、京都市などに出やすい立地です。この交通網の良さから、企業が倉庫や工場を設置している以外にも、大阪市のベッドタウンとして機能しています。
地理について詳しく見てみましょう。茨木市は淀川の北岸に位置しており、北摂地域と呼ばれる場所に位置しています。南北に細長く、北側には老ノ坂山地、北摂山地があるほか、三島地域最高峰で、一等三角点が設置されている石堂ヶ岡(泉原山)が位置しています。そのため自然が豊かではあるものの、山間部で暮らす人は高齢化の一途をたどっており、場所によっては高齢化率40%を超える地域もあります。
南部は、大阪平野の一部である三島平野が広がっており、大阪万博の影響もあって開発が盛んにおこなわれています。大阪市のベッドタウンとしてはこの南部が機能しており、一部老朽化が進んでいるものの、大阪市にも京都市にもアクセスが良いという関係で住宅地が拡大している状況です。また、市の東端部には千里丘陵がかかっており、こちらもニュータウンとして開発された歴史があります。
交通網では、市内に阪急バス、京阪バス、近鉄バスが通っています。北部になると本数は少なくなるものの、市内中心部から主要な施設への移動は公共交通機関で完結する利便性の高さが魅力です。鉄道では、JR西日本の茨木駅をはじめ、阪急京都線の茨木市駅や南茨木駅、大阪モノレールの彩都西駅や阪大病院前駅があります。これらはいずれも大阪万博をきっかけに整備されたもので、現在は老朽化に対する再開発も計画されています。
道路では、名神高速道路や新名神高速道路が通っており、東西どちらにも移動しやすい点が魅力です。また、近畿自動車道や大阪中央環状線もあるため、同じ大阪市内や近畿圏全体へのアクセスも良好です。加えて国道171号線、大阪高槻京都線(産業道路)もあり、一般道での移動も快適にできます。ちなみに、大阪府吹田市にある吹田ジャンクション付近には、茨木市の飛び地が存在しています。現在は縮小しているものの、吹田ジャンクション建設前は、八丁池と呼ばれる池が存在していました。現在はほとんど残っていません。
茨木市の地名の由来は諸説ありますが、イバラの木が多く生えていたためとする説と、「味木の里」が訛ったとする説、坂上田村麻呂が茨を切り取ったことを由来とする「荊切の里」を起源とする説があります。江戸時代の文献にも現在の「茨木」以外に、「茨城」「荊木」「荊切り」と表記しているものも発見されています。
南茨木駅の東側には、弥生時代の大規模環濠集落である東奈良遺跡があり、多数の住居や大型建物の跡が発見されています。また、銅鐸や銅戈などを製造していたとされる工房跡も発見されており、この地で製造された銅製品が近畿一円と四国で発見されています。勾玉も同様に工房で製造されていた形跡が発見されている状況です。古墳群地帯としても有名で、太田茶臼山古墳や阿武山古墳などの古墳も現存しています。
平安時代以降は、市の北部を東西に走る西国街道の往来が盛んになったほか、室町時代には、武将 楠木正成によって茨木城が築城されました。特に茨木城の築城によって栄えた城下町は、現在の茨木市の基礎となっていると言われており、大坂の陣ののち江戸幕府天領となったあとも交通の要衝として繁栄したと言われています。また、安土桃山時代の領主 高山右近はキリシタン大名として知られており、その影響で山間部には隠れキリシタンの里が点在していました。
明治になると、廃藩置県によって大阪府の管轄となり、北部の福井地区ではケシの栽培が盛んにおこなわれていました。1948年に茨木町・三島村・春日村・玉櫛村が合併し、茨木市となります。戦後はベッドタウンとして人口が増えるとともに工場が集積。1970年の大阪万博によって開発が進み、現在の茨木市の姿へとつながります。これらの影響から、マンションや住宅が多く存在するのはもちろん、工場や物流倉庫が現在でも集中するきっかけとなったのです。また、公立・私立を問わず学校が多く存在しているほか、大学も6つ(短期大学を含め7つ)あります。