大阪市での家族葬・葬儀をご検討の方は、吹田市・摂津市・茨木市・箕面市・八尾市など大阪エリアでGoogle口コミ件数No.1などお客様から高い評価をいただいている吹公社までご相談ください。
「大阪市」の家族葬・葬儀なら吹公社へ大阪市で死亡手続きの進め方|届出から関連手続きまで徹底解説

大切な方が亡くなられた際、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。大阪市では、死亡届の提出をはじめとして、年金や健康保険、介護保険など複数の手続きが必要となります。手続きには法律で定められた期限があり、それぞれの優先順位を理解して計画的に進める必要があるのです。
本記事では、大阪市における死亡に関する手続きについて、届出の方法から関連する手続きまで、必要な情報を網羅的に解説します。初めての方でもスムーズに手続きを進められるよう、期限や必要書類、届出場所などを詳しくご案内します。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。
目次
大阪市における死亡届の基本情報
死亡届は、戸籍法に基づいて提出が義務付けられている重要な届出です。大阪市内で死亡された場合、または大阪市に本籍や住所がある方が市外で死亡された場合に提出します。
届出を行うことで、戸籍に死亡の事実が記載され、火葬や埋葬の許可証が発行される仕組みです。適切な期限内に手続きを完了させることが求められるため、基本的な情報をしっかりと把握しておきましょう。
死亡届の用紙は、死亡診断書または死体検案書と一体になっており、医師が記入した書類と併せて提出します。届出が受理されると、火葬許可証が交付され、葬儀や火葬の手配を進めることができます。大阪市では24区すべての区役所で死亡届を受け付けており、時間外窓口も利用可能です。
ただし、時間外は書類の預かりのみとなるため、火葬許可証の発行は翌開庁日となる点に注意が必要です。
死亡届の届出人と資格者
死亡届を提出できる方には、法律で定められた届出義務者と届出資格者があります。誰が届出を行えるのかを事前に確認しておくことで、手続きをスムーズに進められます。それぞれ理解しておきましょう。
届出義務者について
死亡届には、法律で定められた届出義務者が存在します。同居の親族が第一の届出義務者となり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。同居していない親族であっても、届出を行う必要があります。
親族以外では、以下の人が届出義務者に該当します。
- 親族以外の同居者
- 家主、地主または家屋管理人
- 土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 など
医師や助産師が立ち会った場合には、死亡診断書または死体検案書を作成してもらい、死亡届と一緒に提出します。病院で亡くなられた場合は医療機関から、自宅などで亡くなられた場合は検案を経て警察から交付されます。届出義務者が複数いる場合、そのうちの誰か一人が届出を行えば問題ありません。
届出資格者について
届出義務者以外にも、届出資格を持つ方が存在します。親族以外の同居者や、施設で亡くなられた場合はその施設の管理者なども届出可能です。老人ホームや病院などの施設で死亡された場合、施設の職員が届出資格者として手続きを代行することもあります。
葬儀社などの使者による代理提出も認められていますが、届出人欄には実際に届出を行う資格のある方の署名が必要です。使者が届出を行う場合でも、届出人は届出義務者または届出資格者でなければなりません。
届出資格者による届出の場合、届出義務者がいない、または届出義務者による届出が困難な状況において認められます。具体的な状況については、区役所の窓口で相談することをおすすめします。届出人の資格について不明な点がある場合は、事前に確認しておくとスムーズです。
死亡届の提出期限と届出場所
死亡届には法律で定められた提出期限があり、適切な場所で手続きを行う必要があります。期限を守り、最寄りの届出場所を把握しておきましょう。
届出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内となります。この期限は法律で定められており、正当な理由なく遅れた場合には過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
期限を過ぎてしまうと過料が科される可能性があるため、速やかな手続きが重要です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、区役所の窓口で相談することをおすすめします。
死亡の事実を知った日とは、通常は死亡日と同じになりますが、遠方にいて連絡が遅れた場合などは、実際に知らされた日が起算日となります。休日や祝日も提出期限に含まれるため、注意が必要です。期限が迫っている場合は、時間外窓口を利用することも検討しましょう。
届出場所
大阪市内であれば、死亡者の本籍地や届出人の所在地、死亡地のいずれかの区役所で届出が可能です。24区すべての区役所で受け付けているため、最寄りの区役所を利用できます。北区、中央区、西区、天王寺区、浪速区、福島区など、どの区役所でも手続きは同じです。
時間外や休日でも、各区役所の時間外受付窓口で届出を受け付けています。ただし、時間外の場合は書類の預かりのみとなり、内容の確認や火葬許可証の発行は翌開庁日です。
大阪市外に本籍がある方でも、大阪市内で死亡された場合や届出人が大阪市内に住所を有している場合は、大阪市の区役所で届出できます。火葬を急ぐ必要がある場合は、開庁時間内に届出を行うことをおすすめします。届出先に迷った場合は、電話で問い合わせてから訪問すると確実です。
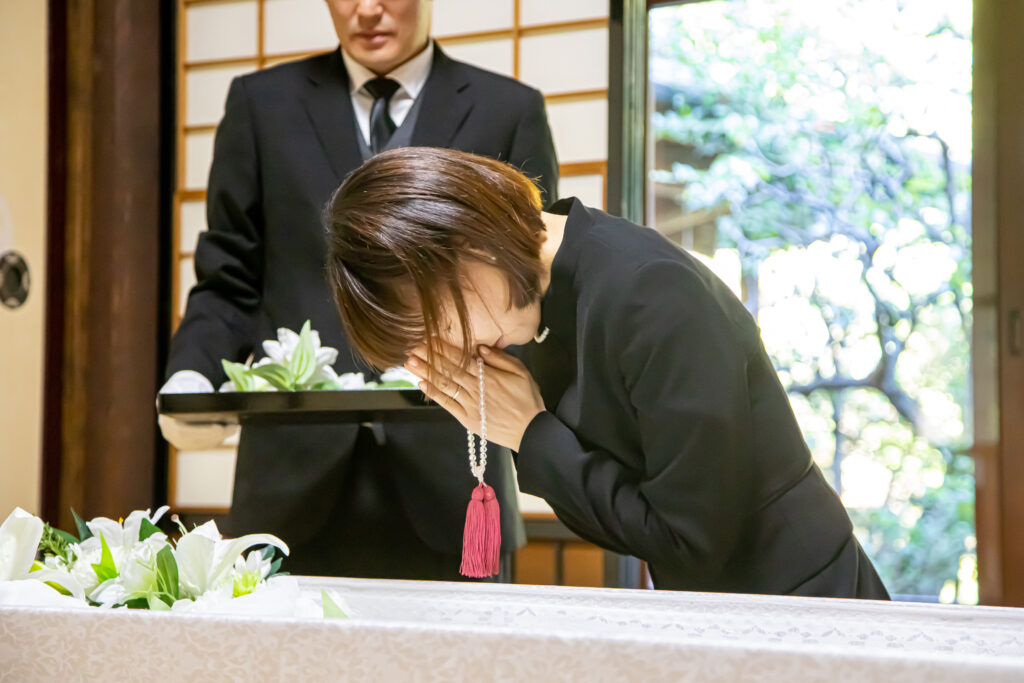
死亡届の提出に必要な書類
死亡届を提出する際には、以下の書類や持ち物が必要です。事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進められるでしょう。
- 死亡届の用紙
- 届出人の印鑑(認印可)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
外国籍の方が亡くなられた場合は、パスポートや在留カードなどの身分証明書が必要となることがあります。詳しくは、届出を行う区役所の窓口で確認してください。
火葬許可証の取得手続き
死亡届を提出すると、埋火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬を行うことができないため、必ず受け取って火葬場に持参しましょう。火葬許可証は、死亡届が受理された後、その場で交付されます。
大阪市内の市立斎場は予約を事前に行う必要があり、葬儀社を通じて手配することが一般的です。市立斎場は市民料金が適用されるため、市外の施設よりも費用を抑えられるでしょう。
火葬後は、火葬済の印が押された埋火葬許可証が返却されます。この証明書は納骨の際に必要となるため、大切に保管してください。紛失すると再発行に時間がかかるため、葬儀が終わった後も厳重に管理しましょう。
火葬場の予約が混み合っている場合、希望する日時に火葬できないこともあります。特に冬季は予約が集中しやすいため、早めの手配が重要です。葬儀社に依頼する場合は、火葬場の予約も含めて相談すると安心です。
死亡に伴う年金関連の手続き
年金を受給していた方が亡くなられた場合、受給停止の手続きが必要です。また、遺族が受け取れる年金給付についても確認しておきましょう。
国民年金の手続き
故人が国民年金に加入していた場合、年金受給の停止手続きが必要です。死亡日から14日以内に年金事務所または区役所の窓口で手続きを行います。手続きが遅れると、過払いが発生して後日返還を求められることがあるため、速やかに届出を行いましょう。
遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金などの給付を受けられる場合があるため、該当する可能性がある方は必ず確認しましょう。必要な書類は、以下のとおりです。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票 など
遺族年金の請求には、死亡診断書のコピーや世帯全員の住民票なども必要となります。
年金を受給していた場合、死亡当月分までの年金は受け取ることができます。未支給年金として、遺族が請求する権利があるため、忘れずに手続きを行ってください。請求できる遺族の順位が定められているため、詳しくは年金事務所で確認しましょう。
厚生年金の手続き
厚生年金を受給していた方が亡くなられた場合も、速やかに年金事務所への届出が必要です。遺族厚生年金の受給資格がある場合は、併せて申請手続きを行います。厚生年金の場合、勤務先を通じて加入していたため、会社の総務部門連絡しておくことをおすすめします。
未支給年金がある場合は、遺族が請求することができます。年金事務所で詳しい説明を受けながら、必要な手続きを進めていきましょう。請求には戸籍謄本や住民票、振込先の口座情報などが必要です。
遺族厚生年金は、一定の要件を満たす配偶者や子が受給できます。受給要件や金額については、個別の状況によって異なるため、年金事務所で相談することが大切です。年金事務所では予約制の相談窓口を設けている場合もあるため、事前に電話で確認しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
国民健康保険に関する手続き
故人が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失の手続きが必要です。死亡日から14日以内に、区役所の保険年金担当窓口で手続きを行います。手続きが遅れると、保険料の請求が続いてしまうため、速やかに届出を行いましょう。
保険証は返却しなければならないため、必ず持参してください。世帯主が亡くなられた場合は、世帯主の変更届も同時に提出する必要があります。家族全員分の保険証を持参すると、必要な手続きを一度で済ませられるでしょう。
葬祭費の支給制度があり、葬儀を執り行った方(喪主)が申請することで、一定額の給付を受けられます。申請期限は葬儀を行った日から2年以内ですが、早めの手続きをおすすめします。申請には、保険証、葬儀の領収書、喪主の口座情報などが必要です。
大阪市の国民健康保険の葬祭費は、5万円が支給されます。申請の際は、葬儀社の領収書や会葬礼状など、喪主であることを証明できる書類を持参してください。区役所の窓口で詳しい説明を受けられます。
【期限別】その他の重要な手続き一覧
死亡届や年金、健康保険以外にも、状況に応じて必要となる手続きがあります。期限ごとに整理して、漏れなく手続きを進めましょう。
死亡後14日以内
世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合は、世帯主変更届を提出しなければなりません。区役所の窓口で手続きを行ってください。
介護保険に加入していた方が亡くなられた場合、介護保険の資格喪失手続きが必要です。介護保険証を返却し、必要に応じて保険料の精算を行ってください。
後期高齢者医療制度に加入していた方は、資格喪失の手続きと保険証の返却が必要です。葬祭費の申請も併せて行えます。
死亡後1か月以内
公共料金の名義変更や解約手続きを進めます。電気、ガス、水道、電話、インターネット回線などの契約について、各事業者に連絡してください。
クレジットカードや銀行口座の解約手続きも必要です。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
運転免許証やパスポートなどの身分証明書は、警察署や旅券事務所に返納します。マイナンバーカードは区役所に返却してください。
死亡後3か月以内
相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。相続財産の状況を把握し、相続するか放棄するかを決定します。
生命保険金の請求手続きを行います。保険会社に連絡し、必要書類を準備して請求してください。請求期限は通常3年ですが、早めの手続きが推奨されます。
死亡後10か月以内
相続税の申告が必要な場合は、税務署への申告と納税を行います。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に申告義務が発生します。
遺産分割協議を行い、相続財産の分配について相続人全員で合意しなければなりません。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成してください。
不動産の相続登記についても準備を進めます。令和6年4月から相続登記が義務化されているため、期限内に手続きを完了させましょう。
まとめ
大阪市で死亡手続きを進める際は、死亡届の提出から始まり、年金、健康保険など様々な手続きが必要となります。それぞれに期限が設けられているため、優先順位を明確にして計画的に進めることが重要です。
まずは死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出し、火葬許可証を取得します。その後、14日以内に国民健康保険や年金、世帯主変更など緊急性の高い手続きを完了させましょう。期限が1か月、3か月、10か月と続く手続きもあるため、リストを作成して管理することをおすすめします。
区役所の窓口や専門家のサポートを活用しながら、必要な手続きを着実に完了させてください。不明な点があれば、遠慮なく区役所の窓口や大阪市総合コールセンターに問い合わせることをおすすめします。大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは大変ですが、一つひとつ確実に進めていきましょう。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。










